おすすめの本
「調べる学習コンクール」連続講座を開催しました!
- 掲載日:2024年8月4日
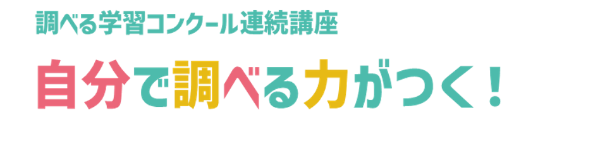
開催日時
令和6年7月7日(日曜日)、21日(日曜日)、26日(金曜日)
参加した人
調べる学習コンクールへの応募を予定している小・中学生など
調べる学習コンクール 作品の作り方を学びました
1日目:調べる学習をやってみよう
講座初日、太陽の照りつける中、講座に申し込んだ小・中学生のみなさんが田無公民館に集いました。

講師の重野先生が最初に見せたのは、1枚の写真。数匹のハチが葉っぱを持って飛んでいる姿が映っています。後で分かりますが、このハチは「ハキリバチ」といって、葉っぱをさまざまな形に切り抜いて、自分たちの巣を作るために河原の岩間に一生懸命運んでいる姿だそうです。
これらのハチは一体何をしているのか?参加者の子どもたちは、この疑問に対して、自分なりの答えを予想します。

次に先生は、2冊の本を読んで、疑問に対して分かったこと書き出すように伝えました。わかりやすい文章にするコツは、友達や家族に説明するつもりで書くこと、絵やイラストもつけること、本に書いてある通りに書き写すのではなく、自分なりの文章に要約することだそうです。
さらに、自分がたてた予想と比べてどうだったのか、その感想もあわせて記入していきます。



そして最後に、調べて分かったことから新たに生まれた疑問を書き出し、また予想→調べた結果、感想→新たな疑問…というように繰り返していくことを伝えました。
"ミニ・調べる学習"を体験した子どもたちは、重野先生からいろいろなことを教わり、楽しかった様子♪
2日目:調べる学習のコツを知ろう
2週間の間をあけて再び田無公民館に集った子どもたち。今日は1日目の最後に出されていた「自分が調べたいと思うテーマを考えよう」という宿題を持ち寄り、実際に調べることになるテーマを踏まえたうえで、調べる学習に応募する作品の書き方を学びました。

重野先生によれば、全国コンクールで賞を受賞する作品には、いくつか共通することがあるそうです。それは下の画像のようなことで、まさに、子どもたちが一日目に体験したことそのものでした。

- 疑問→予想→調べた結果と感想→新たな疑問…というようにつなげていき、作品にストーリー性をもたせること
- 調べてわかったことだけではなく、それが自分のたてた予想と比べてどうだったのか感想を書くこと
- 調べ方は、本だけではなく、実際に博物館等を訪れたり、自分で体験したりする「フィールドワーク」も重要
この3つが特に大切だと、子どもたちに伝えていました。
3日目:個別相談会で自分のテーマを決めよう!
連続講座最終日。この日は個別相談会で、子どもたちは先生と図書館司書と一緒に、自分の調べる作品のテーマを決めていきます。
みんなこれから調べていくテーマは決まったかな?作品作りはここからが本番!自分だけの目標に向かって、最高の思い出をつくろう!!
西東京市図書館を使った「調べる学習コンクール」について
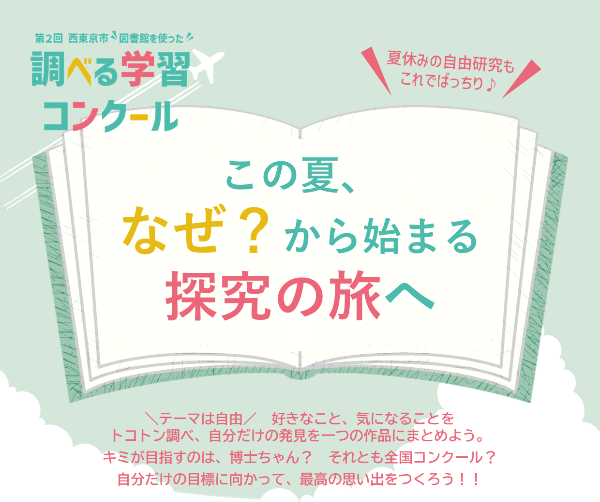
お問い合わせ
西東京市中央図書館(042-465-0823)
